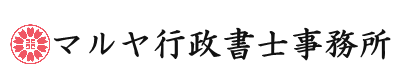1,被相続人が残した自筆証書遺言を発見したときは(法務局の保管制度を利用していないもの)
自筆証書遺言は『検認』が必要になりますので、発見したら絶対に開封しないでください。
相続人が改ざんしたと判断され、自筆証書遺言が無効になる可能性があります。
開封せず、家庭裁判所に『検認の請求』を行なってください。封をしてある自筆証書遺言を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料になります。
罰金は刑事上の刑事罰になりますが、過料は行政上の罰則です。また、誤って開封をしてしまった場合には、速やかに家庭裁判所へ相談していただき、その指示に従って、手続きを進めてください。
2,自筆証書遺言を作成するときの要件
1,遺言者本人が自筆で全文を書く
添付の財産目録を除く
遺言者本人が自筆(手書き)で、全文を書いてください。財産目録を添付する場合、目録についてはパソコンで作成したものでも可能となりました。また、通帳の写しや不動産の登記事項証明書を添付することも可能です。
2,作成した日付を正確に自筆で書く
遺言書を作成した日付を正確に書いてください。「令和6年11月10日、2024年11月10日」など和暦、西暦を問いませんが「令和6年11月吉日」は日にちが特定されないためダメです。また、複数の遺言書が発見された場合新しい日付のものが有効になります。
3,氏名を自筆で書く
条文には規定されていませんが、氏名に加え住所も書くことが望ましいとされています。(遺言者をより特定できるため)
4,印鑑を押す
印影が不明瞭にならないよう、はっきりと押してください。印鑑の種類は問いませんが、スタンプ式はダメです。
5,訂正には印を押し、欄外にどこを訂正したか書いて署名する
間違えたときは→
①訂正する文字を二重線で消し、訂正後の文字を記入してください。
②遺言書に用いた、同じ印鑑を訂正後の文字が見えるように押印。
③加筆箇所の欄外、若しくは遺言書の末尾に〇文字削除、〇文字加筆と記載のうえ、遺言者が自筆にて署名してください。
①訂正する文字を二重線で消し、訂正後の文字を記入してください。
②遺言書に用いた、同じ印鑑を訂正後の文字が見えるように押印。
③加筆箇所の欄外、若しくは遺言書の末尾に〇文字削除、〇文字加筆と記載のうえ、遺言者が自筆にて署名してください。
3,自筆証書遺言の確認事項
| すべて自署で書いた | |
| 日付は特定できる | |
| 署名した | |
| 複数人で署名していない(共同遺言をしていない) | |
| 押印をした | |
|
本文の作成日と日付の押印の日は同一である |
|
| 財産目録を通帳のコピーやパソコンで作成したが、条項ごとに署名、押印をした | |
| 誤字、訂正箇所はない | |
|
誤字はあるが、加除、訂正については、➀その場所を指示し、②これを変更した旨を付記して |
|
| 財産は登記事項証明書、通帳で特定できる | |
| 財産を漏れなく記載したうえで「その他遺言者に属する一切の財産」等の文言を入れた | |
| 相続人、財産を譲る人が、続柄、氏名、生年月日等で特定できる | |
| 「相続させる」「承継させる」「遺贈させる」の用語の使い分けをしている | |
| 遺留分に配慮して、遺留分侵害額請求等の後のトラブルを回避する分割方法としている | |
| 工夫をした付言事項に想いを残し、後のトラブルが起きないように記載している |